「うちの子、まだハイハイしないけど大丈夫?」
周りの赤ちゃんがどんどん動き始める中で、わが子の成長に不安を感じるママ・パパも多いのではないでしょうか?
実は、ハイハイをしない赤ちゃんも珍しくありません。この記事では、ハイハイをしない主な理由や考えられる原因、そしてどんなときに相談すべきかをわかりやすくご紹介します。
赤ちゃんがハイハイをしない原因6つ
赤ちゃんがハイハイをしない原因は6つあります。
- 発達の個人差(正常な範囲)
- 体の発達がゆっくりめなタイプ
- 床での遊びやうつぶせ姿勢が少ない
- 性格や気質によるもの
- 視覚や聴覚の問題(まれなケース)
- 神経や筋肉の発達に関わる疾患(ごくまれ)
1. 発達の個人差(正常な範囲)
もっとも多いのがこのケースです。赤ちゃんの成長には大きな個人差があり、ハイハイを始める時期もさまざま。
- ずりばいで満足している
- ハイハイより先に立ちたがる
- お座りや寝返りが好きで、あえて動こうとしない
こういった赤ちゃんは、移動の意欲が他の方法で満たされていることも。
💡生後10〜11ヶ月ごろまでに、何らかの移動手段ができていれば多くの場合心配はいりません。
2. 体の発達がゆっくりめなタイプ
首すわりや寝返りなどがゆっくりだった赤ちゃんは、ハイハイまでのペースもゆるやかです。
- 筋肉や体幹の発達がまだ不十分
- 姿勢の安定にもう少し時間が必要
このような赤ちゃんは、しっかり動けるようになるまで少し待つことが大切です。
3. 床での遊びやうつぶせ姿勢が少ない
赤ちゃんの動きの発達には、床で自由に動く経験が不可欠です。
- ベビーチェアや抱っこ中心の生活だった
- 家の環境的に床遊びのスペースがとりにくかった
うつぶせになる時間が少ないと筋力や体の使い方を学ぶ機会が減ってしまい、ハイハイが遅れることもあります。
4. 性格や気質によるもの
赤ちゃんにも性格があります。慎重だったり、おっとりしているタイプの子は、動くことにあまり興味を持たないことも。
- 新しい動きに慎重でためらっている
- 手の届く範囲で満足してしまう
- 「今のままでいいや」と思っているかも?
💡「動かない=発達が遅れている」ではなく、その子らしい成長のペースであることがほとんどです。
5. 視覚や聴覚の問題(まれなケース)
視力や聴力に問題があると、まわりへの興味や反応が減り、動こうとする機会も減少します。
- 音や光に対して反応が乏しい
- 呼びかけても気づかないことがある
このような場合は、一度専門医の診察を受けてみると安心です。
6. 神経や筋肉の発達に関わる疾患(ごくまれ)
次のような兆候がある場合は、小児科や発達専門機関への相談をおすすめします。
- 片方の手足だけを使う、極端に動きに左右差がある
- 筋肉がかたすぎる、またはぐにゃぐにゃしている
- 表情が乏しい、呼びかけに反応しない
- 生後11〜12ヶ月になっても移動手段がまったく見られない
これらは神経や筋肉の疾患が隠れている可能性があるため、早めの評価が大切です。
受診前のチェックポイント
以下の点を確認してみましょう。
- ずりばい・寝返り・おすわりなど、他の動きはできているか?
- 表情や反応がしっかりあるか?
- 両手両足をバランスよく使っているか?
- うつぶせ姿勢を極端に嫌がっていないか?
まとめ
ハイハイをしないからといって、すぐに発達異常と結びつける必要はありません。大切なのは、赤ちゃんの「全体的な発達」を見ることです。
発達には幅があり、「ちょっと遅いかも?」と思っても、それがその子の個性ということもよくあります。ただし、不安が強い場合や気になる症状があるときは、小児科や自治体の育児相談窓口に相談してみましょう。
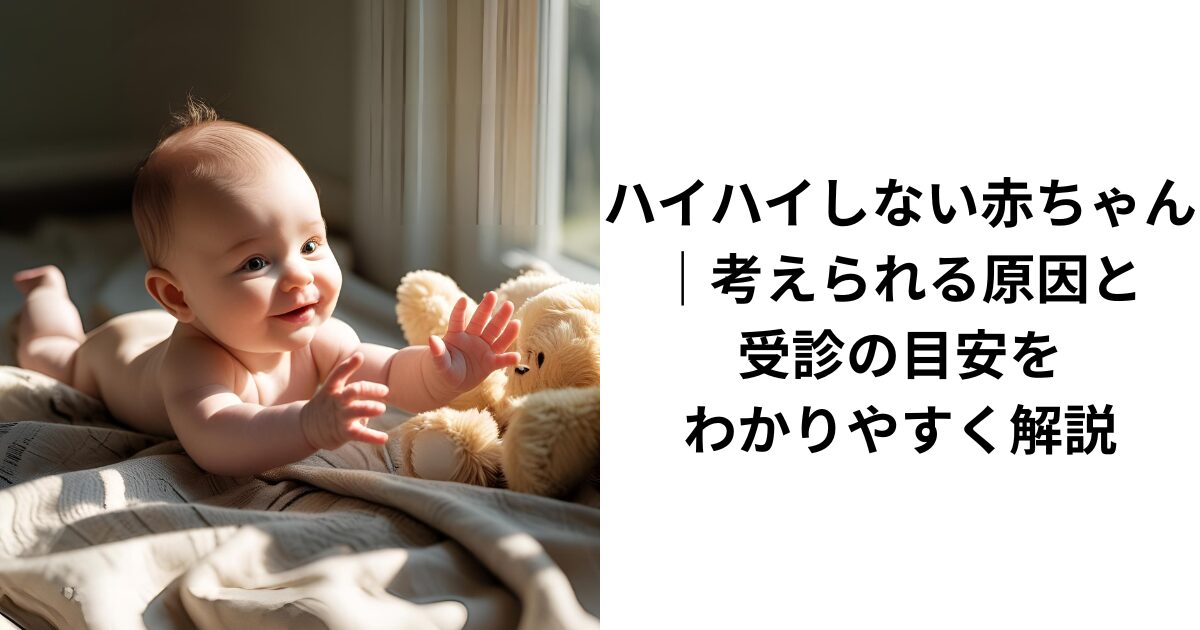


コメント