交通事故や転倒などで「脳挫傷」と診断されたあと、「後遺症が残るかもしれない」と言われて不安になっていませんか?
この記事では、脳挫傷の後遺症とは何か、どんな症状があるのか、回復の見込みや家族としての対応法まで、やさしく丁寧に解説します。
脳挫傷とは?なぜ後遺症が起こるのか
脳挫傷(のうざしょう)とは、交通事故や転倒などで頭を強く打ったときに、脳の組織そのものが傷ついてしまう状態です。脳に出血や腫れが生じ、損傷を受けた部位の機能に障害が出ることがあります。
その結果、脳挫傷の後遺症として、身体的・認知的・感情的なさまざまな問題が現れることがあります。
【一覧】脳挫傷の主な後遺症
1. 記憶障害
- 直前の出来事を覚えていない
- 何度も同じ質問をする
- 日常の予定を忘れる
2. 注意力・集中力の低下
- 話の途中で気が散る
- 二つのことを同時にできない
- 長時間の会話や作業が苦手になる
3. 感情コントロールの問題(易怒性・情緒不安定)
- 怒りっぽくなる
- 突然泣き出す・笑い出す
- 感情の起伏が激しくなる
4. 無気力・うつ症状
- 興味や意欲がなくなる
- 笑わなくなる・活動量が減る
- 「自分はダメだ」と思い込む
5. 遂行機能障害(計画性の低下)
- 段取りができない
- 物事を最後までやり遂げられない
- 優先順位がつけられない
6. 運動障害・しびれ
- 手足が思うように動かない
- 片麻痺や歩行障害が残る場合も
7. 高次脳機能障害
脳の損傷が原因で起こる「見た目ではわかりにくい障害」。記憶、注意、感情、行動など、日常生活に幅広い影響を及ぼします。
脳挫傷の後遺症は回復する?経過とリハビリ
回復には「時間」と「支援」が必要
脳の損傷はすぐには元に戻りませんが、**脳の可塑性(かそせい)**という力により、他の部位が機能を補っていくことがあります。
- 回復の目安:3か月~1年が最も変化しやすい時期
- その後も数年単位での改善が見込めるケースあり
🧩 リハビリ内容の例
- 作業療法(生活動作の訓練)
- 言語聴覚療法(会話・理解・記憶訓練)
- 理学療法(歩行訓練など)
- 認知リハビリ(集中・記憶力トレーニング)
家族や周囲の人ができる関わり方
症状を「病気のせい」と理解する
本人の性格の変化やミスに対して、「なぜできないの?」ではなく、「脳が損傷したせい」と理解することが第一歩です。
責めずに、ゆっくり・具体的に伝える
- 「これをやって」と言うより、「今、これを〇時までにやろうね」
- 一度にたくさんのことを伝えず、メモや図で補助する
安心できる環境をつくる
- 決まったスケジュールで生活する
- 静かな空間で落ち着ける時間をもつ
脳挫傷の後遺症は制度のサポートが受けられる
以下の制度が使える場合があります:
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 麻痺などがある場合に取得可能 |
| 自立支援医療制度 | 医療費の自己負担が軽減される制度 |
| 障害年金 | 働けない場合などに収入保障として申請可能 |
| 高次脳機能障害支援センター | 各都道府県にある専門の支援機関 |
まとめ|脳挫傷の後遺症と向き合うには「理解」と「支援」がカギ
脳挫傷の後遺症は、記憶や感情、意欲の低下など、さまざまな症状が現れることがあります。しかし、見た目には分かりにくく、誤解されがちです。
一人で抱えず、医療・福祉・家族のサポートを活用することが回復への第一歩です。
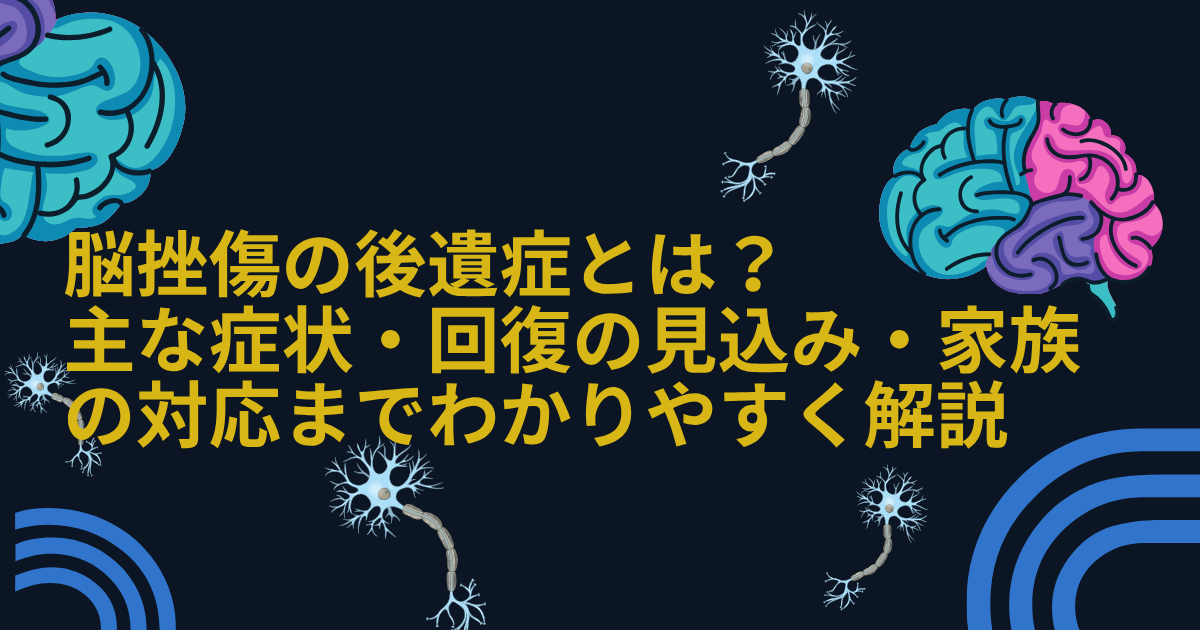


コメント