赤ちゃんの成長を見守る中で、「首がすわるのはいつ?」「まだ首がすわらないけど大丈夫?」と心配になる親御さんも多いのではないでしょうか。
今回は【首すわりの時期・確認方法・遅れがある場合の対処法】について、わかりやすく解説します。
首すわりとは?どんな状態?
「首すわり」とは、赤ちゃんが自分の力で頭を支えられる状態のことをいいます。生まれたばかりの赤ちゃんは首の筋肉が未発達なため、頭がグラグラしていて自分で支えることができません。
首すわりが完了すると、抱っこがしやすくなり、体の発達や運動の幅も広がっていきます。
首すわりはいつから?平均的な時期
- 生後3ヶ月ごろ:首が少し安定してくる
- 生後4ヶ月ごろ:縦抱きでもしっかり支えられるように
- 生後5ヶ月ごろ:ほとんどの赤ちゃんが首すわり完了
【ポイント】
赤ちゃんの成長には個人差があります。早い子では2ヶ月台から首が安定し、逆に5〜6ヶ月かかる子もいます。
首すわりのチェック方法
赤ちゃんの「首すわり」が進んでいるかどうかを確認するには、以下の3つの方法がよく使われます。簡単にできるチェックばかりなので、日々の育児の中で試してみましょう。
1. 【縦抱きでチェック】頭がグラグラしないか確認
赤ちゃんを肩のあたりに抱き上げて、縦に抱っこしてみましょう。
✔︎チェックのポイント
- 親の肩に赤ちゃんの頭を預けた状態で、首がガクンと後ろに倒れないかを見る。
- 赤ちゃんが自分の力で頭を支えているようであればOK。
- 横から見たときに、首・背中・頭が一直線になっていれば、かなり安定しています。
※まだ首がすわっていない場合は、必ず首の後ろに手を添えて支えてください。
2. 【うつ伏せ遊び(腹ばい)でチェック】頭を持ち上げられるか?
柔らかいマットや布団の上に赤ちゃんをうつ伏せにしてみる方法です(生後2ヶ月ごろから少しずつチャレンジ可能)。
✔︎チェックのポイント
- 自分の力で頭を持ち上げて左右に動かすことができていれば、首の筋肉がしっかりしてきています。
- 視線を合わせると、目で追いながら頭を動かす様子も見られることがあります。
✔︎注意点
- 初めは数秒でもOK。嫌がる場合は無理せず、機嫌のよいタイミングで短時間から始めることが大切。
- 必ず大人がそばについて安全を確保してください。
この遊びは「タミータイム」とも呼ばれ、首・背中・腕の筋力発達にとても効果的です。
3. 【引き起こし反応(プル・トゥ・シット)】頭がついてくるか?
赤ちゃんを仰向けに寝かせ、両手を優しく握って、上半身を少し引き起こす方法です。
✔︎チェックのポイント
- 首がすわっていないと、頭だけ後ろにカックンと遅れてついてくる。
- 首がすわりかけていると、頭が体と一緒に持ち上がるようになってくる。
- 完全に首がすわると、頭の遅れなくスムーズに一緒に動きます。
✔︎注意点
- ゆっくりとした動きで行い、赤ちゃんの様子をよく観察しながら。
- 無理に引っ張らず、赤ちゃんの反応を尊重してください。
首すわりが遅いのはなぜ?原因と考えられること
首すわりが6ヶ月を過ぎても見られない場合は、発達の遅れや筋力の弱さが考えられます。以下のような原因があるかもしれません。
1. 低出生体重児(2,500g未満)や早産児だった場合
- 赤ちゃんが在胎週数よりも早く生まれた場合(早産)や、出生時の体重が小さかった場合(低出生体重児)は、成長のペースがゆっくりになる傾向があります。
- こうした赤ちゃんは、「修正月齢」で発達を見る必要があります。たとえば、予定日より1ヶ月早く生まれた赤ちゃんなら、生後6ヶ月でも修正月齢は5ヶ月として評価されます。
✅ 修正月齢を使えば「遅れていない」と判断されるケースも多いです。
2. 運動量が少ない・環境による影響
- 常に抱っこやベビーチェアに入っている、うつ伏せの時間が少ないなど、体を動かす機会が少ないと、筋力や神経の発達に影響することがあります。
- 特に、うつ伏せの姿勢(タミータイム)を嫌がるからと避けていると、首を使う機会が不足してしまうことも。
✅ 適度なフリームーブメント(自由な動き)が発達にはとても大切です。
3. 筋力・神経系の発達がゆっくりな体質
- 特別な疾患がなくても、筋肉や神経系の成熟に時間がかかる子もいます。こうした子は、寝返りやおすわり、はいはいも少し遅めになることがあります。
- 遺伝的な体質や、のんびりした性格の傾向も関係している場合があります。
✅ 機嫌がよく、体重増加や視線の反応など他の発達に問題がない場合は、経過観察になることが多いです。
4. まれに見られる医療的な要因
以下のようなケースでは、医師による早期の評価とフォローが必要です。
- 明らかに筋緊張が弱い・力が入らない(常にふにゃふにゃしている)
- 手足の動きが左右で極端に違う、または片側しか動かさない
- 表情が乏しく、目線が合いにくいなど、神経系の発達にも疑問がある
このような場合、筋疾患、脳性麻痺、染色体異常などが関係している可能性もあるため、専門の医師に相談を。
心配なときの対応:どこに相談すればいい?
● 乳児健診(4ヶ月健診・6〜7ヶ月健診など)
- 健診では発達のチェックも行われ、必要があれば発達専門外来やリハビリ相談をすすめられることもあります。
- 医師や保健師に、日頃気になっていることを遠慮なく伝えましょう。
● 小児科
- 健診を待たずに、心配な場合は小児科にいつでも相談してOK。
- 必要があれば、発達を専門とする小児神経科やリハビリ科への紹介も受けられます。
● 地域の子育て支援センターや保健センター
- 保健師・助産師が在籍しており、家庭訪問や電話相談で発達のサポートをしてくれることもあります。
首すわりを促す遊びやトレーニング
赤ちゃんの首すわりをスムーズに促すためには、無理なく楽しめる遊びや日常の関わりがとても大切です。ここでは、家庭で簡単にできるトレーニング方法をご紹介します。
■ 1. うつ伏せ遊び(タミータイム)
うつ伏せで過ごす時間は、首すわりの発達にもっとも効果的とされています。
● やり方
- 赤ちゃんを清潔で柔らかいマットや布団の上にうつ伏せにします。
- 初めは1日数回、1〜2分からスタート。
- 慣れてきたら、5分〜10分程度を数回行ってもOK。
● ねらい
- 首・肩・背中・腕の筋力を総合的に強化できます。
- 頭を持ち上げる力が自然と育ち、首すわりに必要な筋力が育つ。
● ポイント&注意点
- 赤ちゃんの顔の前におもちゃや鏡、お母さんの顔を置いて、興味をひくと◎。
- 機嫌がよい時に行うことが重要です。
- 赤ちゃんが泣いたり苦しそうな様子なら、すぐにやめましょう。
- 目を離さず、常にそばで見守ることが大前提です。
■ 2. 自由な手足の運動(フリームーブメント)
赤ちゃんを布団やプレイマットの上に寝かせて、自由に動ける時間を増やすことで、自然と筋肉が育ちます。
● やり方
- おくるみやベビーチェアから出して、自由に動ける状態にしてあげましょう。
- 特に仰向け→寝返り→うつ伏せの動きが出てくると、首や体幹の発達が進みます。
● おすすめの関わり方
- 赤ちゃんの手足を優しく「にぎにぎ」「ぱたぱた」してあげる。
- 音が鳴るおもちゃや布のおもちゃを使って、手を伸ばす・振る動きを促す。
● ねらい
- 自発的な動きの中で、首だけでなく全身の連動した発達を促進します。
■ 3. 声かけ&アイコンタクト
赤ちゃんは、パパやママの表情・声・目線に強く反応します。これを活かして首の動きを促すことができます。
● やり方
- 赤ちゃんの正面や左右に立ち、名前を呼んだり、歌を歌ったりします。
- 赤ちゃんが顔や目線を向ける方向に移動しながら声をかけると、自然と首を動かします。
● ねらい
- 「見たい!」「聞きたい!」という興味から首を自発的に動かす練習になります。
- 視線を合わせることで、愛着形成や安心感にもつながります。
■ 4. 縦抱き&胸の上での密着タイム
首すわり前は縦抱きを避けがちですが、正しく支えて行えば筋肉刺激として有効です。
● やり方
- 赤ちゃんの首と背中をしっかり支えながら、短時間の縦抱きをします。
- もしくは、パパやママが仰向けに寝転び、その胸の上に赤ちゃんをうつ伏せにのせるスタイルもおすすめ(スキンシップにも◎)。
● 効果
- 赤ちゃんは「頭を起こしてパパママの顔を見よう」とし、首の筋肉に自然な刺激が入ります。
■ 5. ボール遊びやバランス運動(4ヶ月以降)
首がある程度安定してきたら、体を少し動かす遊びも取り入れてみましょう。
● 例:バランスボールに寝かせてゆらゆら
- 赤ちゃんを仰向けやうつ伏せでボールに乗せて、優しく前後左右に揺らします。
- バランスをとるために、首や体幹を使おうとする動きが生まれます。
※必ず大人がしっかり支えて行ってください。
首すわり後の変化と注意点
首すわりが完了すると縦抱きがしやすくなり、視野も広がって赤ちゃんの活動が活発になります。しかし、首がすわったとはいえ、まだまだ体全体のバランスは発展途上です。以下の点には十分注意しましょう。
⚠️ 1. 激しい揺れや急な動きはNG
赤ちゃんの首が安定してきたからといって、激しく揺らしたり、縦に跳ねるような動きは避けましょう。
- 頭は重たく、首や背中に負荷がかかりやすい
- 未発達な脳や神経にダメージを与えるおそれがある
特に、ソファやベッドの上でのジャンプ遊び、赤ちゃんを高く持ち上げて落とすような遊びは避けてください。
⚠️ 2. 長時間の座位・歩行器はNG
赤ちゃんの首がすわると、「そろそろおすわりの練習を…」「歩行器に入れてあげようかな?」と思う方もいるかもしれませんが、時期尚早に長時間座らせるのは危険です。
■ 座位(おすわり)
- 背中や骨盤の筋肉が未発達な状態で長く座らせると、姿勢が崩れて疲れやすくなる
- おすわりは自然にできるようになるまで待つことが基本です(生後6〜8ヶ月ごろ)
■ 歩行器
- 見た目には楽しそうに見えますが、無理な立位が脚・骨盤・姿勢に負担をかけます
- また、転倒や段差による事故のリスクもあります
※育児の手助けとして一時的に使う場合でも、短時間・安全な場所で・必ず見守ることが必要です。
⚠️ 3. 発達を焦らないことが何より大切
「もう首がすわったから○○もできるはず」と、先に進もうとする気持ちはとても自然ですが、赤ちゃんの発達は一人ひとり異なります。
- すわる・寝返る・立つ・歩くなどのプロセスは順序と準備が必要です。
- 焦らず、「できるようになる過程」を楽しむ姿勢が親子にとって最良の関わり方です。
まとめ:首すわりは赤ちゃんの第一歩
首がすわると、赤ちゃんの視野も動きもぐっと広がり世界が変わります。これは「ゴール」ではなく「これからの成長の土台ができた」という段階であり、赤ちゃんが次の成長段階へ進むための重要なステップです。
日々の関わりの中で、安全に・焦らず、日々の育児の中で自然な成長を見守ってあげましょう。
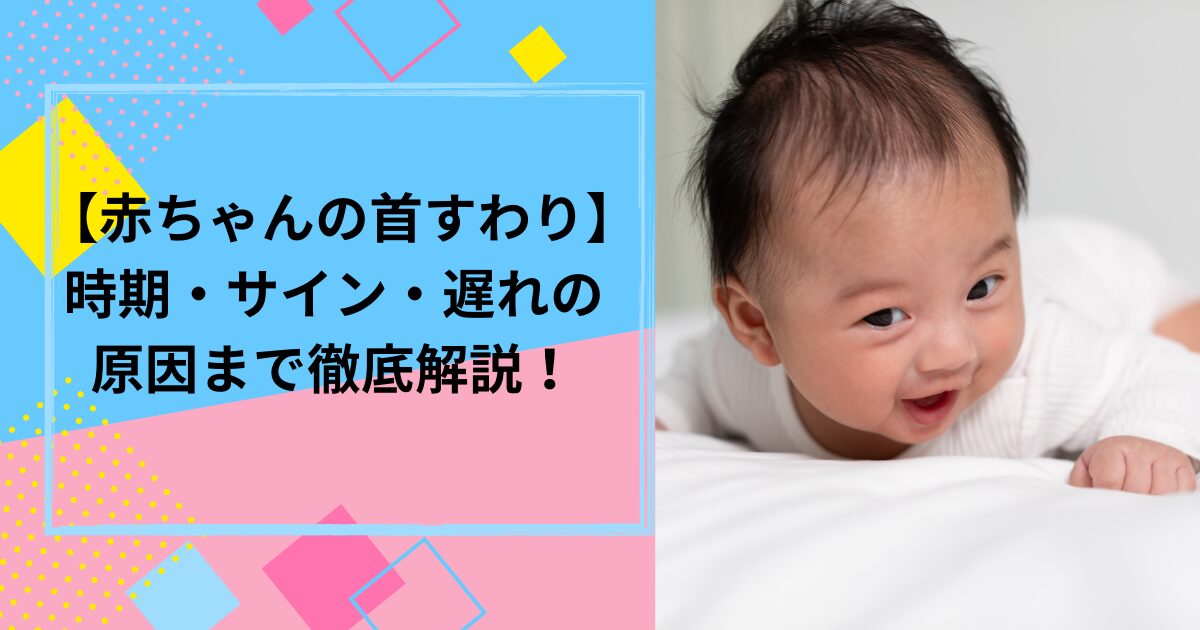


コメント