「けいれん=てんかん?」と不安になる保護者の方も多いかもしれません。
てんかんは、脳の神経活動に一時的な異常が起きることで発作を繰り返す病気です。実は、てんかんの発症が最も多いのは小児期(乳児〜学童期)であり、早期発見と正しい対応がとても大切です。
しかし、子どものてんかん発作は大人と違って「ぼーっとする」「転ぶだけ」など目立ちにくい症状も多く、見逃されがちです。また、「熱性けいれん」との違いが分かりにくいこともあります。
このブログでは、子どものてんかんについて、
- 症状や種類(欠神発作・ミオクロニー発作など)
- 「熱性けいれん」との違い
- 原因や診断法(脳波・MRI)
- 治療法や日常生活での注意点
などをわかりやすく解説します。
お子さんの体調や行動に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
「てんかん」ってなに?子どもにも起こるの?
てんかんとは、脳の神経に一時的な異常が起こり、けいれんや意識の消失などの発作を繰り返す病気です。日本では約100人に1人がてんかんを持っていると言われており、発症年齢がもっとも多いのは小児期です。
乳児や幼児の段階で発症するケースもあり、早期発見・早期対応がとても大切です。
子どものてんかんの症状とは?
子どものてんかん発作は、大人と比べて一見してわかりにくい場合があります。代表的な症状には以下のようなものがあります。
よく見られる症状
- 突然ぼーっとして動きが止まる(欠神発作)
- 手足がピクッと動く(ミオクロニー発作)
- 全身が硬直しけいれん(強直間代発作)
- 目をパチパチさせたり、口をもぐもぐさせる(部分発作)
- 突然転倒する(脱力発作)
一時的に意識がなくなるだけの発作も
「ただぼーっとしているだけ?」と思われがちですが、短時間の意識消失もてんかんの可能性があります。特に短時間の発作が頻繁に起こる場合は要注意です。
「熱性けいれん」と「てんかん」の違い
小さなお子さんで最も多いけいれんは「熱性けいれん」です。これは発熱に伴って一時的にけいれんが起きるもので、てんかんとは異なります。
| 比較項目 | 熱性けいれん | てんかん |
|---|---|---|
| 発作の原因 | 熱が出たとき | 特にきっかけがないことも多い |
| 年齢 | 生後6か月~5歳くらいまで | どの年齢でも起こるが、乳幼児に多い |
| 発作の繰り返し | 熱が出たときだけ | 発熱がなくても繰り返す |
| 基本的な対応 | 経過観察が中心 | 専門的な診断と治療が必要 |
子どものてんかんの原因とは?
子どものてんかんは、原因がはっきりしない「特発性てんかん」と、脳の異常がある「症候性てんかん」に分けられます。
特発性てんかん
- 遺伝的な体質が関係していることが多い
- 成長とともに発作が消えることもある
症候性てんかん
- 脳のけが、出産時のトラブル、脳腫瘍、感染症などが原因
- MRIや脳波検査で異常が見つかることがある
どうやって診断するの?
小児てんかんの検査方法
- 脳波検査(EEG)
- 発作時の脳の電気的な変化を測定します。
- MRI(脳の画像検査)
- 脳の構造的な異常を調べます。
- 問診・発作の記録
- 家族が撮影した動画や発作日誌も診断の参考になります。
子どものてんかんの治療法
1. 抗てんかん薬(AED)
- 多くの子どもは1種類の薬で発作がコントロール可能です。
- 毎日決まった時間に服用することが重要です。
2. 食事療法(ケトン食など)
- 難治性てんかんに対して有効な場合があります。
3. 外科的治療
- 薬でコントロールできない場合に検討されます。
日常生活で気をつけたいこと
子どもがてんかんを持っていても、正しく対応すれば普通の生活が可能です。
- 薬は決まった時間に確実に飲む
- 寝不足・ストレスを避ける
- 学校や保育園と情報を共有する
- 発作時の対応方法をまわりの人に伝える
- プール・自転車・高所などは医師の指示に従って安全確保を
まとめ|子どものてんかんと上手につきあうために
子どものてんかんは、珍しい病気ではありません。正しい診断と治療を受けることで、多くの子どもが発作をコントロールし、元気に成長しています。
「もしかしててんかん?」と感じたら、早めに小児神経科やてんかん専門医のいる医療機関に相談しましょう。
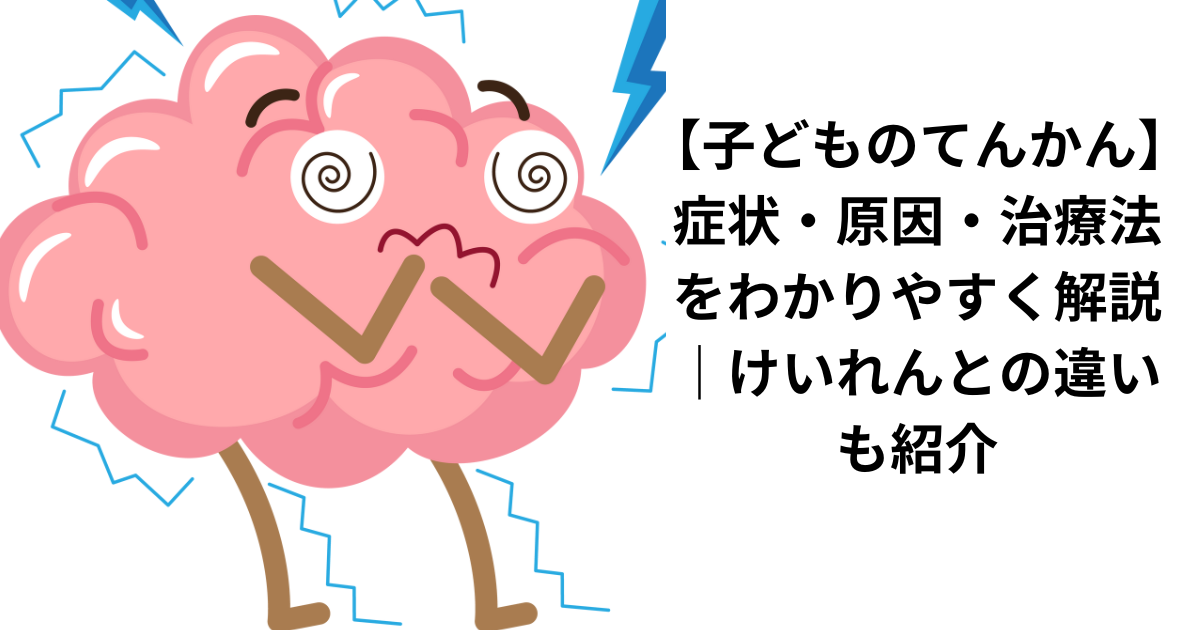
コメント