「高次脳機能障害」と診断されて不安を感じていませんか?
名前が難しそうに見えますが、実は交通事故や脳卒中などで誰にでも起こり得る障害です。
この記事では、高次脳機能障害とは何かから、よくある症状・原因・リハビリ方法・利用できる支援制度まで、医療や介護の専門知識がない方にも分かりやすく解説します。
高次脳機能障害とは?|見た目では分からない脳の障害
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、事故や病気によって脳の一部が損傷し、「記憶」「注意」「感情」「行動」などの高度な機能に障害が出る状態を指します。
外見には障害がないように見えるため、「見えない障害」とも呼ばれ、周囲に理解されにくい特徴があります。
高次脳機能障害の主な原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 脳挫傷 | 交通事故・転倒などで頭を強く打ったとき |
| 脳出血・脳梗塞 | 脳の血管が破れたり詰まったとき |
| 脳炎・脳症 | ウイルス感染や自己免疫の異常による炎症 |
| 心肺停止 | 脳への酸素供給が途絶えたとき(低酸素脳症) |
| 脳腫瘍や手術後 | 脳へのダメージや手術の影響 |
高次脳機能障害の主な症状一覧
1. 記憶障害
- 新しいことが覚えられない
- 約束や会話をすぐに忘れる
2. 注意障害
- 気が散りやすく集中できない
- 一度に複数のことができない
3. 遂行機能障害(計画力の低下)
- 段取りや優先順位をつけられない
- 一つの作業をやり切れない
4. 社会的行動の障害
- 感情が不安定になり、怒りっぽくなる
- 子どもっぽくなり、我慢ができなくなる
5. 自己認識の低下(病識の欠如)
- 自分に障害があるという自覚がない
- できない理由を他人のせいにする
高次脳機能障害は治るの?回復の見込みは?
完全に元通りになるとは限りませんが、適切なリハビリや周囲の支援によって、日常生活や社会復帰が可能になるケースも多くあります。
回復のポイント
- 発症から3〜6か月が最も回復しやすい時期
- 1年以上かけて少しずつ改善することも
- 回復には「本人の努力+周囲の理解と工夫」が不可欠
高次脳機能障害のリハビリ・支援方法
| リハビリの種類 | 目的と内容 |
|---|---|
| 作業療法(OT) | 日常動作の練習、生活リズムの整備 |
| 言語療法(ST) | 会話・理解力・記憶力のトレーニング |
| 認知リハビリ | 注意力・思考力のトレーニング |
| 心理的支援 | 感情コントロールや対人スキルの訓練 |
💡 自宅での生活でも、メモ・予定表・ルーティンの設定が有効です。
家族ができるサポートとは?
✅ 接し方のコツ
- 短く、具体的に伝える
- 繰り返し説明しても責めない
- スケジュールやToDoを「見える化」する
- 成功体験を積ませて自己肯定感を育む
✅ NG対応
- 「なんでできないの?」と責める
- 無理に“元通り”を求める
- 感情的になって衝突する
利用できる制度・支援機関
| 制度・支援名 | 内容 |
|---|---|
| 高次脳機能障害支援センター | 各都道府県に設置、相談・情報提供を実施 |
| 障害者手帳(身体・精神) | 医療費・交通・就労などの支援が受けられる |
| 自立支援医療制度 | 通院費が軽減される |
| 就労支援(A型・B型・移行支援) | 働きながら回復を支援する事業所制度 |
まとめ|高次脳機能障害は「理解」と「支援」で暮らしやすくなる
高次脳機能障害は誰にでも起こり得る障害であり、見た目では分からないからこそ、周囲の理解が大切です。 完全に元の状態に戻らなくてもリハビリや支援制度を活用して、生活を整えることで社会復帰が可能です。家族・支援者も一人で悩まず、地域の「高次脳機能障害支援センター」「保健所」「相談支援事業所」などの専門機関や福祉サービスに相談しましょう。
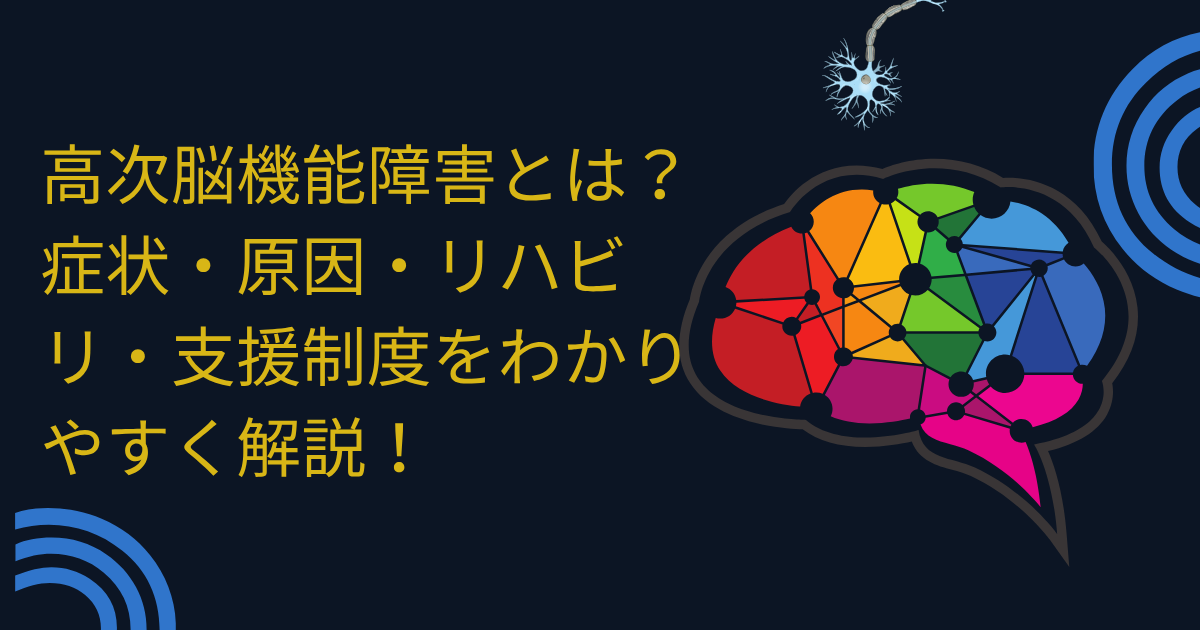


コメント